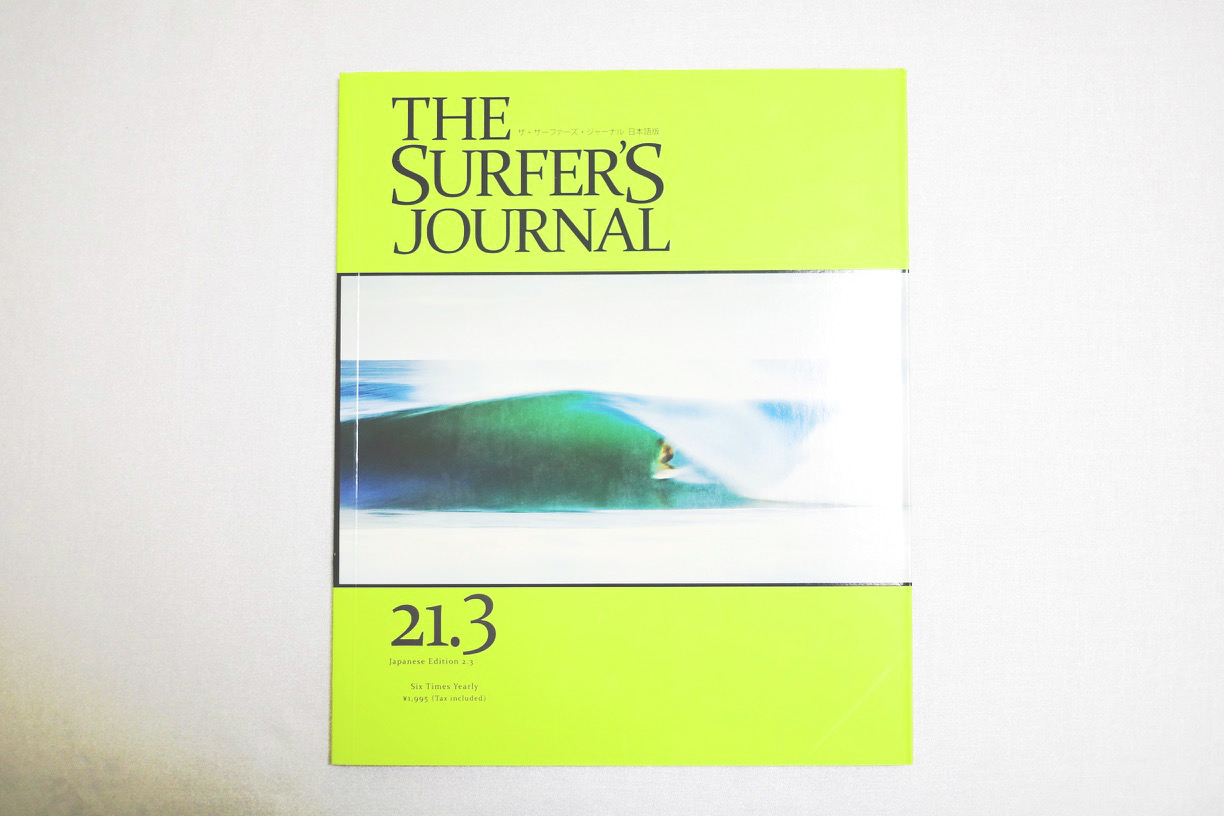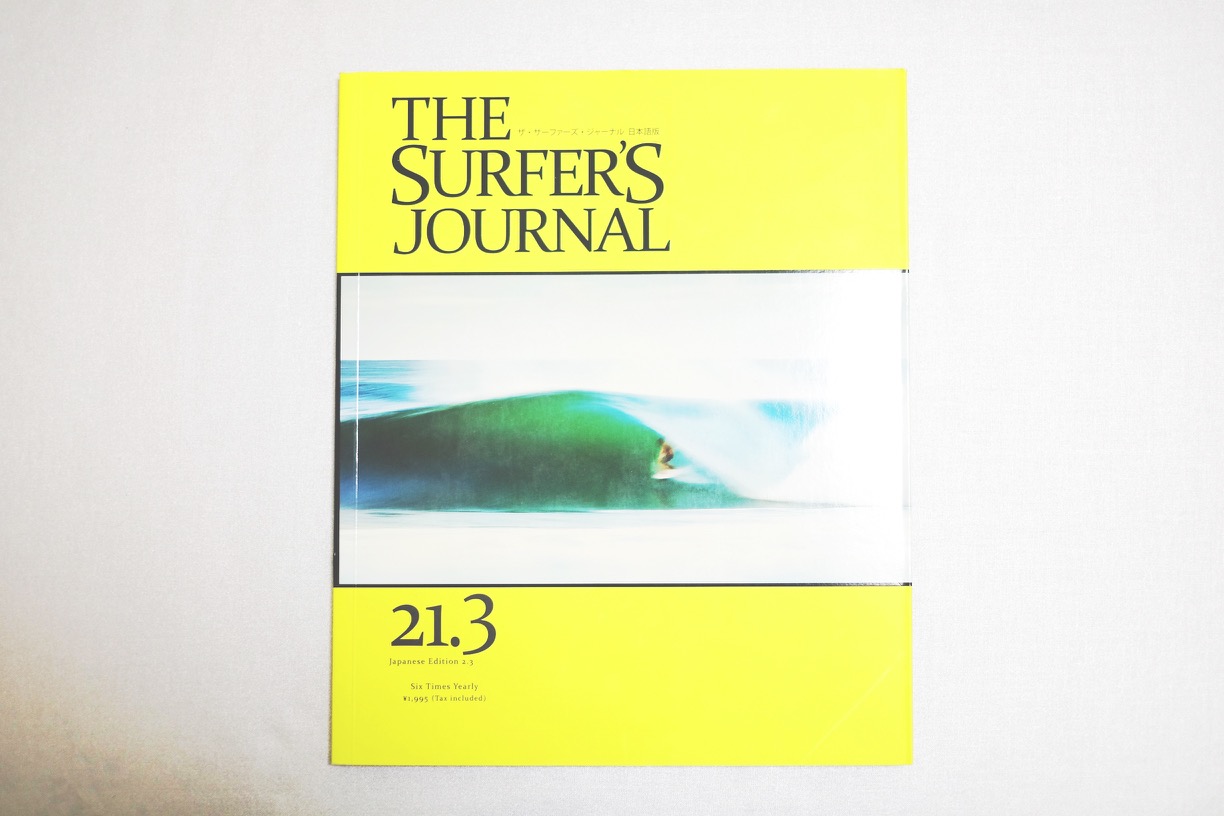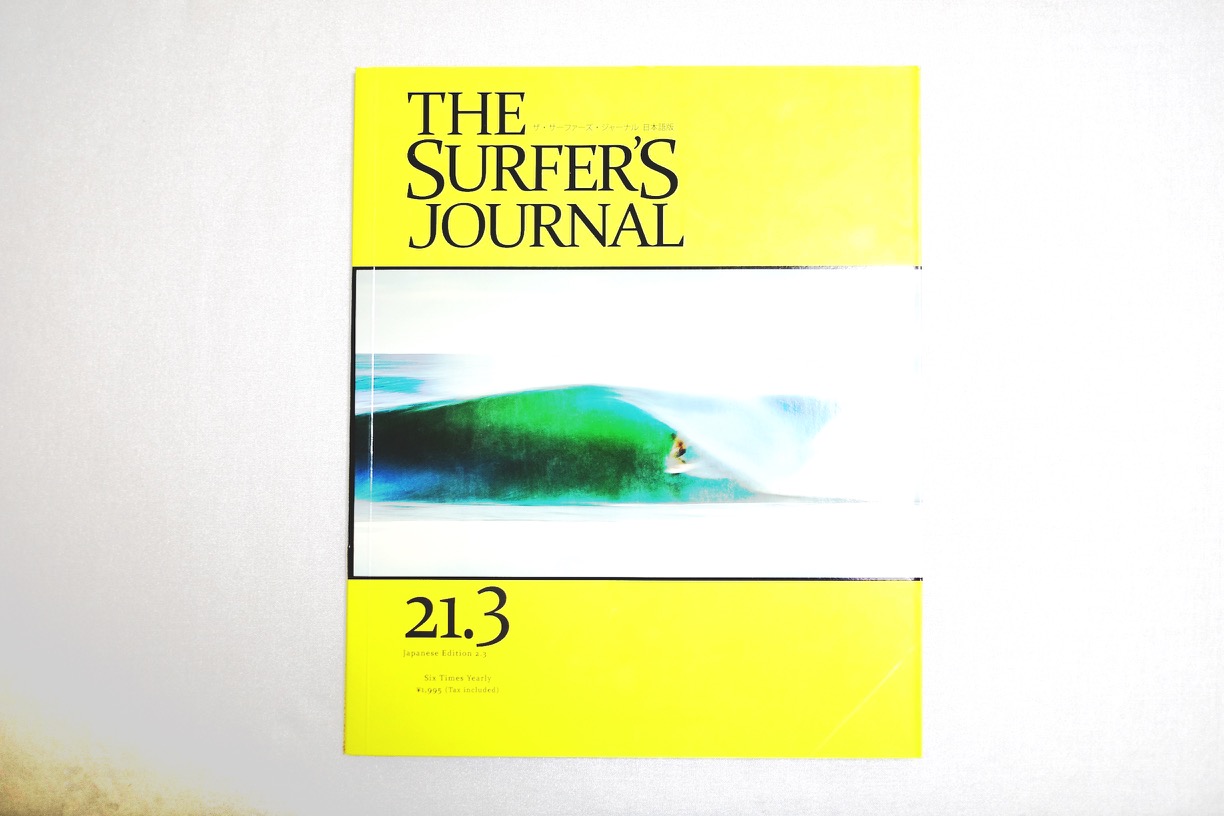ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版Volume2 No.3 » The Surfer’s Journal ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版
http://www.surfersjournal.jp/archives/855
【ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版Volume2 No.3】
2012/08/10発売号 English Edition Volume 21 No.3
【Liner Notes / 解説 By スティーブ・ペズマン】ミジェット・ファレリーはサーフメディアのことを、基本的には不信感を持った目で、良く言えば無関心な目で眺めている。よく耳にする理屈として聞くのは、ショートボード革命時代にメディアが彼のことを時代遅れのロングボード乗りのシンボルとして扱ったからだというものだ。逆にナット・ヤングやボブ・マクタビッシュ、テッド・スペンサーやウェイン・リンチといった人々は、フィルムやメディアでは新しい世界に挑戦している連中として扱われていた。その状況を苦々しく思ったミジェットは、車の後部座席に貯まった埃の中にあえて留まったのだと思われて来た。だが実は、ミジェットのサーフィンは決して停滞してはいなかった。いつも流動的で実験的。時には他の人以上に鮮やかだった。彼の個性にはパワフルな知性を強く持つスペシャリスト・サーファーとしての一貫性があった。彼が活躍した頃から何十年も後になるが、本誌では、何人かのサーフライターたちによるその時代のミジェットの評価を何回か掲載した。その中には彼の立場、彼の気持ちの分析、爆発、他の人たちからの、「ミジェットがなぜ隠遁生活を享受するのか?」に対する意見、さらにはナットやマクタビッシュからの真実の過去をもっと露出して欲しい旨の嘆願などが綴られてきた。そう、みんなでもう一度、あのムーブメントを生み出した張本人としてミジェットを再評価し、レトロ・セレブレーションの壁を再構築して欲しいと心底思う。一方ミジェット自身の世界は、彼自身ビジネスでは成功を収めたし、ひとつの地球儀を回して…そこはカナダ沿海州のイルデフォグスだ。シーンに迎合することなく人生にも成功した。その成功はとても大きなものだったので、サーフカルチャーを無視しても全然平気だったのだ。友人との交流と知的刺激は他のエリアで見つけてきた。だから今流行りのレトロ・サーフフレンジーからは、彼自身が意識的に遠ざかってきたようにも思える。マーク・オナーティから、自分の写真を起用しミジェットが執筆した、若いオーストラリアのクラシック・スタイル・ロングボーダーのプロファイルを載せてみないかと提案された時、私たちはそのアイデアに飛びついた。ミジェットがこれほどエネルギーをかたむけ、他のサーファーを語るということは稀であり、このチャンスは何が何でもミスできないと思ったためだ。
クレッグ・ロックウッドのビル・オグデンに関する記事はまったく違う。私たちの世界では滅多に出現することのない類の、細心の注意で細工され描かれた彼のロマンティックなジオラマは凄いけれど、それでも彼の生活はギリギリだ。オグデンは、ラグーナ・ビーチにあるサウンドスペクトラム・スタジオのオーナーであるジミー・オットーが、自分のスタジオのプロモーション用ポスターを発注したことでスポットライトが当たった人物だ。1960年代の後半のことである。それは、オットー独特の世界観やその時代の音楽とスタイルを哲学的にアプローチするためのひとつの方法だった。そのおかげで、アーティストたちもある程度は世界に知られるようになった。ビル・オグデンは彼が選んだアーティストの中のひとり。今ではそのサウンドスペクトラムのポスターはコレクターズ・アイテムになっている。それ以来ビルは、一貫性を持った独特なアートワークをイラストとファインアートがミックスされた独特なタッチでプロデュースし、今まで彼なりのスタイルを磨いて来た。その道を進みながら何人かのパトロンにも出会い、そのパトロンたちは彼のアートに魅せられ、彼をヘルプしつつマーケットを提供し、彼をただ絵を描いていれば良い状態に置いてあげようとした。彼はそういう生き方に向いていたのだ。最近は、ニューポート・ビーチのサーファーで、サーフィン・ヘリテージ・ファウンデーションに所属するスペンサー・クロウルが彼をフォローする。スペンサーは今号に掲載された絵をコミッションし、ビルの名前をもう1度世界に紹介しようとプロモートしている。特集では大きな絵画を描くオグデンのプロセスを掲載し、その才能の証しと呼んで差し支えないアートを紹介する。記事の筆者であるロックウッドも、ファインアートの世界から登場してきた人物だ。ビルと同じ時代、同じエリアで暮らしたラグーナ・ビーチのガロの息子である。ふたりはパーフェクトにフィットできたと思う。仕上がった記事の内容は、ひょっとするとアメリカン・アーティスト・マガジン向きだったかもしれないけれど、ビルのエピックは、どんなサーファーの心にも響くことだろう。
ビル・オグデンとスペンサー・クロウルの共存関係のように、TSJは読者の皆さんのお陰で素晴らしい仕事が残せています。皆さんに感謝しています。̶ スティーブ・ペズマン